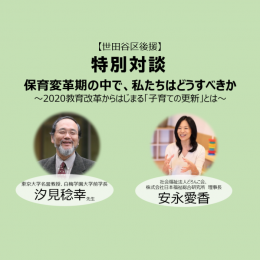古河市主催「児童発達支援講演会」に安永理事長と八山田どろんこ保育園の施設長が登壇
2024.09.12
2024年7月20日、茨城県古河市主催の「令和6年度児童発達支援講演会」に、どろんこ会グループの安永理事長と八山田どろんこ保育園(福島県郡山市)の真島施設長が登壇しました。

今回の講演は、発達支援が必要な子どもを特別視することなく、地域の中で当たり前に保育・支援していく環境について考えることを目的に児童発達支援センターの方が企画。そこで、保育園と児童発達支援事業所の併設施設を全国各地で運営するなど、業界に先駆けてインクルーシブ保育を実践しているどろんこ会グループに登壇のご依頼をいただきました。
講演会は2部構成とし、1部では安永理事長より法人としてのインクルーシブ保育の考え方を、2部では併設施設である八山田どろんこ保育園の真島施設長から、現場実践の事例をお話しました。
当日は、古河市内で児童発達支援や保育に従事されている方を中心に、インクルーシブ保育に興味のある約100名の方々にご参加いただきました。
障害児こそ、トラブルを含めたさまざまな経験が必要
第1部のテーマは「なぜインクルーシブ保育が必要か。どう実践するか」。
安永理事長は、日本が保育所等保育指針や発達支援ガイドラインにて、時代に即した教育指針を打ち出しているにもかかわらず、保育・教育現場が実践していないことが問題であると指摘し、今後は現場の対応を変えていく必要があることを説明しました。

特に、障害児や発達に気がかりがある子どもについて、大人が特別扱いをしてしまうことへの影響についても言及しました。
「障害児は感情のコントロールや人との関わりを苦手とする子が多いが、それらの力は実際に経験を積まなければ身につかないため、障害児として早期に生活の場を分離すると経験の機会を奪うことになります。そして、障害を理由に活動を制限・指定することを続けると、子どもが自分の好きなものや得意なことを知るなどの自己探索が十分にできないため、将来職業選択にも影響が出てしまいます」
トラブルを回避するために活動の制限や指定をすることは大人の都合であり、子どもの成長を妨げるため直ちにやめること、そして障害児こそ健常児よりも多くの経験が必要であることを訴えました。
子どもを変えるのではなく、大人の対応を変えていく
第2部のテーマは「施設長に聞く!インクルーシブ保育園の試行錯誤と失敗、乗り越えてきたプロセス」。
今回は保育・発達支援に従事する方の参加が多いため、参加者が明日から活用できる、現場でのリアルな実践事例を伝えることを目的に、八山田どろんこ保育園の真島施設長が登壇。施設での取り組みについて、写真や動画で実際の様子をお見せしながら紹介しました。

八山田どろんこ保育園は発達支援つむぎ 八山田ルームを併設し、2021年に福島県郡山市に開所しました。
併設施設では、保育園のスタッフは保育園の子どもだけを見るといった分担はせず、スタッフの所属にかかわらず全ての子どもを支援しています。しかし、最初からインクルーシブ保育を実践できていたわけではなく、当初は保育士と発達支援の専門士でスタッフの連携が難しかったことを明かしました。スタッフ同士で対話を重ねたり、業務の見える化をした上で業務分担を行いながら相互理解を深めていき、今では両施設のスタッフが自然と集まり、子どもの様子を話し合うようになりました。

また、八山田どろんこ保育園で子どもの変化や成長を感じたエピソードについて紹介。異年齢・インクルーシブ保育を行う中で、トラブルが生じても子ども同士で解決方法を考える姿や、思い通りにいかないことがあっても気持ちに折り合いを付ける力が育まれていくプロセスを説明しました。
真島施設長は、発達支援において子どもは何らかの困りごとを抱えており、困っているのは大人ではなく子どもであることを説明。子どもができないことに目を向けるのではなく、何に困っているのかを見ることが必要であり、子どもを変えるのではなく、大人の対応を変えていく必要があることを伝えました。

講演後のアンケートでは多くの方から「参考になった」との感想が寄せられました。
世界や政府が政策を考えている中で、現場の保育が変わらないという点に共感しました。中堅の自分ですが、昔の考えの良いところはそのままで、今に合った保育を取り入れていきたいと改めて思いました。
今まで、グレーの子をどうにか分類しようとしたり、個別対応をしたりの支援をしていた。「その子のため」と思っていたが、生きる力を奪っていたことを感じた。人格形成は8歳までは変化することを知ることができたので、とても良い学びになった。
どろんこ会グループでは、今後もインクルーシブ保育のフロントランナーとして多くの現場実践を積みながら社会へ広く発信することで、インクルーシブ保育の推進に努めてまいります。
インクルーシブ保育に関する視察・お問い合わせ
当グループの併設施設やインクルーシブ保育に関する視察・お問い合わせにつきましては、以下お問い合わせフォームよりご連絡ください。
関連リンク
「あたらしい保育イニシアチブ2023」にて「認可保育園の中に児童発達支援事業所をつくってみた。」をテーマに講演しました