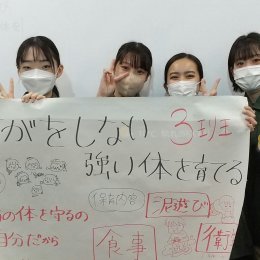保育園の食を守る調理の現場から 新卒スタッフの調理研修に密着
2022.04.06
どろんこ会グループの子どもたちの大切な「食」を任されている調理スタッフ。
4月1日から現場に立つ新卒入社の調理スタッフだけを集めた調理研修を3月に実施しました。スタッフは5箇所の施設に分かれて集まり、午前はオンラインで講義を受け、午後は実際に施設のキッチンに入っての厨房研修という、充実の一日となりました。

子どもの命、安全を守るために基本事項をしっかりと
講義の冒頭、今回の研修を統括した八山田どろんこ保育園(福島県郡山市)で管理栄養士を務める滝田さんは「私たち調理スタッフのベースにあるのは、きちんと調理し、子どもたちに安心・安全な食事を届け、子どもたちの命を守ることです。そのために必要なことは、基礎的な知識、マニュアルの順守、そして日々の丁寧な仕事だと思っています。今日お話することは学校でも習ったかもしれませんが、今一度基礎を確認し、どろんこ会グループでの仕事の土台をつくりましょう」と参加者に向けて優しく語りかけました。

早速、浦安どろんこ保育園(千葉県浦安市)の管理栄養士であり食育プランナーも務める小田島さんから衛生に関する講義からスタートです。ちなみに食育プランナーとは、どろんこ会グループの給食調理に関する衛生面および食のプロフェッショナルであり、給食のレシピも考案するスタッフを指します。小田島さんは現場で実践している立場から分かりやすく消毒液の作り方や包丁やまな板の使い分け、加熱や冷却の温度測定の具体的なルールといった調理室で守るべきことなど、多岐にわたり細かな点まで伝えました。
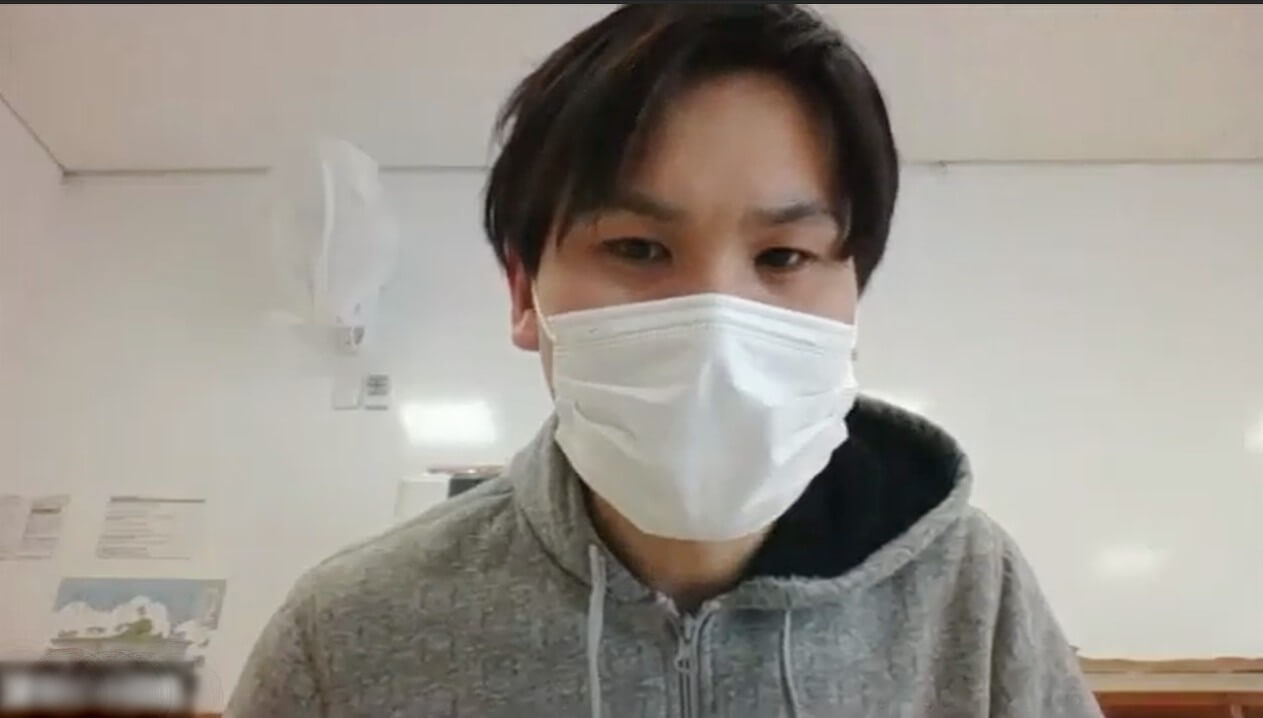
続いて仲町どろんこ保育園(埼玉県朝霞市)の管理栄養士兼食育プランナーの大脇さんから離乳食についての講義を受けました。離乳食については家庭と園が連携をとるために、それぞれの時期に合わせた食材などを記した書面があります。その運用の仕方を丁寧に伝えたうえで「書類にある離乳食の進め方の区分はあくまで目安です。月齢が7カ月を過ぎたから自動的に中期食に移行するということではありません。あくまで一人ひとりの発達に応じて対応していきましょう」と、個々の発達を見ることの大切さを強調しました。

離乳食は実は学校でも作る機会が少ないそうです。そのため、新卒入社スタッフにとっては未知の世界。しかし、食と保育というのは別々の領域ではなく、子どもたちの「生きる力」の基礎を育むものです。乳幼児期の食の充実は、食生活の基礎をつくるだけではなく、その子の心の発達の土台をつくることにもつながっているという背景を踏まえ、「離乳食に丁寧に取り組むと子どものその後の食への意欲も全く変わってくるというのが私たちの実感です。なので、先輩にいろいろ教えてもらいながら時間をかけて覚えてください」と滝田さんからもアドバイスがありました。
滝田さんはそのほか検品の仕方や食材の発注に関すること、献立表の見方、そして命に直結するアレルギー対応について、特にポイントとなることを重点的に説明しつつ、「いろいろ細かいことを伝えていますがすべてを暗記する必要はありません。『なぜそうするのか』『なぜしてはいけないのか』を常に考えながら仕事をし、現場に入った時に『あの時に聞いたことはこういうことだったのか』と一つ一つ結びつけてもらえればと思っています」と結び、午前の講義は終了です。
素材のおいしさを知り、食育の心構えを学んだ実習
午後は各現場で実際にキッチンに入り、午前中に学んだことを振り返りつつ実習です。
実習は仲町どろんこ保育園(埼玉県朝霞市)、清瀬どろんこ保育園(東京都清瀬市)、北千住どろんこ保育園(東京都足立区)、船橋どろんこ保育園(千葉県船橋市)、読売ランド前どろんこ保育園(神奈川県川崎市)でそれぞれ行いました。

読売ランド前どろんこ保育園のキッチンで講師を務めたのは、4月から同園の調理を任される栄養士で食育プランナーの須田さん。まずは白衣の着替え方、手洗いの仕方といった基本に始まり、午前中に聞いた冷蔵庫の温度の確認や、まな板や包丁の収納についても実際に確認していきました。

この日は実際に以下のことに取り組みました。
- だしの取り方
- 野菜の洗い方
- 野菜の切り方
- 手づかみ食べ野菜の作り方
基礎的なことでも、施設のキッチンのガスの火の強さや調整の仕方、鍋などの調理器具の扱い方、ゆでるには鍋なのかスチームコンベクションを使う方がよいのか、白衣のポケットに常備しておくと便利なものなど、現場で経験を積んだ須田さんならではのきめ細やかなアドバイスに、5人の参加者はうなずきながらメモを一生懸命取ります。

野菜の切り方一つとっても、玉ねぎの芯の部分をいかに無駄を少なくするように切るか、須田さんがプロの工夫を実演します。また、離乳食で使う野菜は繊維を断つように切るのか、繊維に沿って切るのかは個々の発達によって切り方を変えるとよいという知識であったり、にんじんもいちょう切り、短冊切りなどさまざまな切り方を体験しながら、歯ごたえを残したいときは太千切りというような、子どもの成長に応じた使い分けについても学びました。

ゆで方については皮をむき洗った野菜を丸ごと鍋に入れ、ひたひたの水量で柔らかくなるまでじっくり火にかけること約45分。乳児には手づかみで食べれるような太さに切ります。実際にゆでた野菜を試食してみたところ・・・
「素材だけでこんなにおいしいなんて!」
「これまで実は生のにんじんしか食べられなかったのですが、この甘さに驚きました。本当においしい」
と驚きの声が上がりました。

「今、そのように感じている舌を大事にしてください。素材の味を引き出せる調理法を学ぶことも大事です」とほほ笑む須田さん。

また、参加者からはこんな感想も。
「実はにんじんが得意ではなかったのですが、みんなで一緒に食べてみたらおいしかったです」
それに対しても「やはり子どもたちも好きな友達がおいしそうに食べているのを見ると、苦手な食材にも挑戦してみようという気持ちが生まれます。なので信頼している先生が一緒に食べる姿を見せることも大切にしてもらいたいと思います。私たち調理する側はどうしても食べてもらいたいという気持ちが出てきますが、それよりも食べているその時間が楽しいと思ってもらえることが大事なのです」と、須田さんが現場で大切にしている心構えも話しました。
ホンモノを伝えるどろんこの食育を学ぶ
厨房での研修内容のポイントについて滝田さんに聞いてみました。
「調理の現場はめまぐるしく、さまざまな作業を同時進行して最終的に同じタイミングで仕上げなければなりません。学校では調理実習がありますが、たいていはグループで取り組むので、最初から最後までの手順を一人でこなすことはあまりないと思います。そのため全体の流れをつかんだり、見通しを立てることにしばらくは苦労すると思います。これはある程度経験しないと難しいとは思いますので、まずは野菜と仲良くなることが大事だということを伝えようと思いました。どろんこ会グループの給食はとにかく野菜をふんだんに使います。なので、仕込みの方法や切り方が分からないと現場に入った時に大変なのです」と笑います。

また、だしを取ること、味見で使用した食器にも意味がありました。
「どろんこ会グループでは給食はほぼすべて手作りです。だしも昆布、かつお、いりこなどできちんと取ります。カレーライスやハヤシライスでさえルウから作ります。簡単にしようと思えば何でもできるのです。例えばかぼちゃも冷凍のものを使うことだってできます。でも、ホンモノを伝えたいと思っています。子どものために一から丁寧に手間をかけられるスタッフがどろんこ会グループの施設の食を担っています。ホンモノという点では食器も同じです。味見でも使った食器は子どもたちが日ごろ使っているもので陶器です。落としても割れない物にすればよいのかもしれないけれど、毎日使うものだからこそホンモノのよさを感じてもらいたいという法人の考えがあるのです」と滝田さん。

読売ランド前どろんこ保育園での研修に参加した内定者からはこんな感想が聞かれました。
- すでに現場のOJTに入って流れは理解していましたが、あらためてなぜこの作業をやっているのかの理由づけができました。
- 午前中の講義で聞いたことを具体的に教えてもらい勉強になりました。
- なぜこうしなければならないのかということを丁寧に教えていただき、つながりが分かりました。
- 離乳食については学校で実習できなかったので、ゆでる時間の違いなども学べてよかったです。
須田さんは「自分が新人だった時のことを思い出して、当時知りたいと思ったことを伝えられるように話しました。この先忙しくなるとどうしても大人の目線になってしまいがちですが、あくまでも子どもをまん中に考えること、素材を味わうことがなぜ大事なのかということが伝われば」と研修を振り返りました。

滝田さんも「最初からうまくいくことはなく、現場に入ったら分からないことや迷うこと、失敗することもたくさんあると思います。そういう時に恐れず正直にコミュニケーションをとれるような人であってください」とエールを贈りました。
研修を終えた新卒入社スタッフたちの表情は、どろんこ会グループの食育のこれからを担う意欲と期待に満ちているようでした。